1. はじめに
「今の会社、大丈夫かな……?」
最近、建設業界で働く人の間で「人手不足倒産」という言葉をよく耳にします。実際にニュースでも、「人手不足の影響で受注できず倒産する企業が増加」と報じられることが増えてきました。
しかし、こんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか?
•本当に倒産が増えているのか?
•建設業界の人手不足はどれほど深刻なのか?
•自分の会社は大丈夫なのか?
この記事では、最新のデータや現場の声をもとに、建設業界の倒産状況と人手不足の実態を解説します。また、人手不足倒産を防ぐために企業や個人ができる対策も紹介します。
この記事を読むことで、今後の建設業界の動向や、自分のキャリアをどう考えるべきかが分かるはずです。
2. 建設業界の倒産状況
2024年の建設業倒産データ
建設業界の倒産件数は年々増加しており、2024年には1,890件の倒産が発生しました。これは過去10年間で最多の件数です。
特に中小企業の倒産が目立ち、負債総額は1,984億円に達しています。これは前年より7.6%増加しており、業界全体の厳しさが浮き彫りになっています。
倒産の内訳(業種別)
•職別工事業(大工・とび職など):879件
•総合工事業(土木・建築など):600件
•設備工事業(電気・給排水など):411件
特に、内装や設備工事を手掛ける企業の倒産が増えており、資材価格の高騰や人手不足が大きな影響を与えています。
2025年1月の建設業倒産データ
最新のデータを見ても、倒産の増加傾向は止まっていません。
2025年1月には170件の倒産が発生し、前年同月比37.1%増となりました。倒産件数は5カ月連続で増加しており、厳しい状況が続いています。
特に増えている業種
•職別工事業(内装・設備など):57件 → 84件(約1.5倍)
•総合工事業:前年より増加
このデータからも分かる通り、建設業界の倒産はもはや一時的な問題ではなく、長期的な課題となっています。
倒産の主な原因
なぜ、ここまで建設業の倒産が増えているのでしょうか?主な原因は以下の3つです。
① 物価高・資材価格の高騰
2024年に発生した建設業の倒産のうち、約13%(250件)が「物価高倒産」とされています。
建設資材の価格は近年高騰を続けており、特に鉄筋やコンクリート、木材などの価格上昇が顕著です。
しかし、**建設業界の価格転嫁率は43.7%**と全業種平均(44.9%)を下回っており、資材価格の上昇分を工事価格に十分に反映できていません。そのため、利益を確保できずに資金繰りが悪化し、倒産に至るケースが増えています。
② 人手不足による受注減少
人手不足の影響で、受注したくてもできない建設会社が増えています。
2024年には、「人手不足倒産」が99件発生しました。
これは、必要な職人や施工管理者が確保できず、工事を受けられずに業績が悪化するケースです。
特に2024年4月から適用された「時間外労働の上限規制(2024年問題)」の影響で、残業が制限され、施工スケジュールの調整が困難になったことも拍車をかけています。
③ ゼロゼロ融資の返済負担
コロナ禍で中小企業を支援するために実施された「ゼロゼロ融資」(実質無利子・無担保融資)の返済が本格化し、多くの建設会社の経営を圧迫しています。
2024年には、「ゼロゼロ融資後倒産」が143件発生しました。
売上が回復しない中で融資の返済が重なり、資金繰りが行き詰まった企業が次々と倒産しています。
今後の見通し
現在の傾向が続けば、2025年以降も建設業の倒産は高水準が続くと予測されています。
特に、「2025年問題」(団塊世代の大量引退)が直撃することで、さらに人手不足が深刻化する可能性があります。
また、高リスク企業とされる建設業者は約2万8,000社に上ると推定されており、今後1年以内に倒産する企業がさらに増える可能性もあります。
「倒産は大企業の話でしょ?」
「うちの会社は影響ないんじゃない?」
そう考えている方もいるかもしれません。
しかし、実際には中小の建設会社が最も影響を受けているのです。
次の章では、「人手不足の実態」について詳しく解説します。
3. 建設業界の人手不足の実態
深刻な人手不足は本当か?データで見る現状
「建設業界は人手不足」と言われていますが、それは本当に深刻なのでしょうか?実際のデータを見てみましょう。
① 建設業就業者の減少
建設業界で働く人は年々減少しており、ピーク時(1997年)に685万人いた就業者は、2023年には483万人まで減少しました。これはピーク時の約70%にあたります。
さらに、特に現場の作業を担う**「建設技能者」**の数は、1997年の464万人から2023年には307万人まで減少しており、人手不足の深刻さが伺えます。
② 若手不足と高齢化
建設業界の高齢化も大きな問題です。
•55歳以上の割合:36%(全産業平均より高い)
•29歳以下の割合:12%(全産業平均より低い)
•65歳以上の建設技能者:51.1万人(全体の約25%)
つまり、現場で働く職人の約4人に1人が65歳以上であり、10年後には大量の引退者が出ることが予測されています。一方、**若手(29歳以下)はたったの12%**しかいません。
このままでは、高齢者が引退した後、現場を支える人がいなくなる可能性が高いのです。
③ 求人倍率の高さ
建設業界では、働き手が少ないため、求人倍率が異常に高い状況が続いています。
•建設業全体の有効求人倍率:5.34倍(全業種平均1.25倍の4倍以上)
•職種別の有効求人倍率
•建設躯体工事従事者:8.70倍(最も高い)
•土木作業従事者:6.49倍
•建築・土木・測量技術者:5.78倍
特に、職人(建設躯体工事)や施工管理(建築・土木技術者)の人手不足が深刻で、仕事を探す人1人に対して約9社が求人を出している状態です。
なぜ人手不足が起きているのか?原因を分析
① 3K(きつい・汚い・危険)のイメージが根強い
建設業界は長年、「きつい・汚い・危険」のイメージが強く、若者の就職希望が少ない傾向にあります。
実際に、新卒で建設業に就職した高卒の**離職率は42.4%**と、全産業平均(37.0%)より高く、定着率の低さが問題になっています。
② 労働環境の問題(長時間労働・休日の少なさ)
•時間外労働が多い(2024年問題による規制)
•完全週休2日制の導入が遅れている
•現場によっては夏場の過酷な環境
2024年から時間外労働の上限規制が適用され、1ヶ月45時間・年360時間の上限が設定されました。
しかし、これにより「残業ができずに工期が延びる」「人手が足りず仕事を受けられない」という新たな問題が発生しています。
③ 賃金の問題
「建設業は給料が高い」というイメージを持つ人もいますが、実は職種や働き方によって大きく差があります。
建設業の平均年収(国税庁「民間給与実態統計調査」より)
•全業種平均:433万円
•建設業全体:507万円(平均より高め)
•建設技能者(職人):450万円前後
•施工管理(技術職):600万円前後
確かに平均年収は高めですが、これは残業代込みのケースが多く、2024年問題で残業規制がかかると収入が減る可能性があります。
また、未経験者や若手の初任給は低めであり、「給料が安いのにキツい仕事」という印象を持たれやすく、離職率が高くなっています。
人手不足は今後どうなるのか?
① 2025年問題(団塊世代の引退)でさらに深刻化
団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」が直撃し、建設業界では90万人の労働力不足が予測されています。
これにより、以下の問題が発生すると考えられます。
•ベテラン職人の引退で、技術の継承が困難に
•施工管理者・現場監督が不足し、現場が回らなくなる
•企業の受注が減少し、倒産が増える
② 外国人労働者の増加は解決策になるのか?
現在、建設業界では約14.5万人の外国人労働者が働いており、その数は年々増えています。
•技能実習生が約6割を占める
•特定技能の外国人労働者も増加中(2028年までに最大82万人受け入れ予定)
•ベトナム・フィリピン・インドネシアの出身者が多い
政府は「特定技能」制度を活用し、今後さらに外国人労働者の受け入れを拡大する方針ですが、言語や文化の壁、教育の問題などが課題になっています。
まとめ:人手不足はもはや避けられない現実
•建設業の就業者はピーク時の約70%に減少
•55歳以上のベテランが多く、若手はわずか12%
•求人倍率は5.34倍、特に施工管理や職人は8倍以上
•労働環境や給与面の課題で若手が定着しにくい
•2025年問題でさらに人手不足が深刻化
このままでは、建設業界の人手不足は今後さらに加速し、倒産する企業も増えていく可能性が高いです。
では、この人手不足をどう乗り越えればいいのか?
次の章では、「人手不足倒産を防ぐために企業や個人ができる対策」を詳しく解説します。
4. 人手不足倒産を防ぐために
建設業界の人手不足はもはや避けられない問題ですが、だからといって何も対策しなければ倒産のリスクが高まる一方です。
ここでは、企業・個人がそれぞれできる対策について解説します。
4-1. 企業ができる対策
① ICT(情報通信技術)の導入で業務効率化
「人が足りないなら、少ない人数で回せるようにすればいい」
建設業界では今、ICT(情報通信技術)を活用して業務効率を上げる動きが加速しています。
具体的な施策
•施工管理アプリの導入:現場の進捗管理をデジタル化し、無駄な移動や確認作業を削減
•ドローンの活用:測量や点検作業を自動化し、作業時間を短縮
•BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の活用:設計・施工管理を3Dデータ化し、施工ミスや手戻りを減らす
導入事例
大手ゼネコンではすでにBIMを活用し、設計変更のミスを30%以上削減する効果が出ています。
ポイント
「ICTは難しそう」と思うかもしれませんが、最近では中小企業向けの簡単な施工管理アプリも登場しています。まずは無料トライアルなどを活用し、業務効率化の第一歩を踏み出しましょう。
② 働き方改革で人材の定着を図る
「人が辞めない環境を作る」ことも重要です。
具体的な改善策
•週休2日制の導入:休みが少ないと若手が定着しない
•労働時間の管理徹底:2024年問題(残業規制)に対応しながら、生産性を向上
•給与体系の見直し:特に若手の初任給を改善し、離職率を下げる
成功事例
ある中小建設会社では、週休2日制を導入した結果、若手社員の定着率が30%向上したという報告もあります。
③ 外国人労働者の活用
「若手の日本人が増えないなら、外国人を活用する」
現在、建設業界では約14.5万人の外国人労働者が働いており、今後も増える見込みです。
主な施策
•技能実習生の受け入れ:ベトナム・フィリピン・インドネシアからの技能実習生が中心
•特定技能制度の活用:長期的に働ける外国人労働者を受け入れる
•日本語教育の強化:外国人労働者とのコミュニケーションを円滑にする
課題
外国人労働者を雇うには、言語や文化の壁があるため、教育体制の整備が重要になります。しかし、外国人労働者を受け入れた企業の中には、「まじめで定着率が高い」と評価しているケースも多いです。
4-2. 個人ができる対策
「うちの会社、やばいかも……」
もし、あなたがそう感じているなら、今すぐに行動を起こすべきです。
① 転職するべきか?見極めのポイント
「この会社にいて大丈夫か?」と悩んだら、以下のポイントをチェックしてください。
✅ 会社の財務状況は安定しているか?
✅ 人手不足で受注できない状況になっていないか?
✅ 給与・労働環境が改善される見込みはあるか?
もし、これらの状況が悪化しているなら、早めに転職を検討するのが賢明です。
転職するなら、どんな会社を選ぶべき?
•ICTを導入している会社(効率化が進んでいる)
•労働環境が整備されている会社(週休2日制・残業管理がしっかりしている)
•若手が活躍している会社(育成制度が整っている)
建設業界は今、人手不足のため、経験者なら転職市場での需要が高いです。「求人があるうちに動く」ことを意識しましょう。
② 今の会社で生き残るためにできること
「転職はまだ考えていない。でも、このままじゃ不安……」
そんな人は、今の会社で生き残るためのスキルアップを意識しましょう。
おすすめのスキル
•施工管理技士の資格取得(給与アップ・転職の武器になる)
•ICTツールの活用スキル(施工管理アプリやBIMなど)
•外国人労働者とのコミュニケーションスキル(今後、外国人と一緒に働く機会が増える)
特に、施工管理技士の資格を持っていると、転職市場でも有利になるので、今後のキャリアを考えるなら早めに取得を目指すのがおすすめです。
まとめ:人手不足は避けられないが、対策次第で生き残れる
✅ 企業ができる対策
•ICTを活用して業務効率化
•週休2日制など、働きやすい環境づくり
•外国人労働者の受け入れ強化
✅ 個人ができる対策
•転職するかどうかを見極める
•資格取得やICTスキルの習得でキャリアアップ
建設業界の人手不足は今後さらに深刻化しますが、企業も個人も「生き残るための対策」をすれば未来は変わるはずです。
では、この先の建設業界はどうなっていくのでしょうか?
次の章では、「建設業界の未来と今後の展望」について解説します。
5. まとめ・今後の展望
建設業界の未来はどうなるのか?
ここまで解説してきたように、建設業界の人手不足と倒産の問題は深刻な状況です。
では、今後の建設業界はどのようになっていくのでしょうか?
今後の建設業界に影響を与える3つの要因
✅ 2025年問題(団塊世代の大量引退) → さらに人手不足が加速
✅ ICT・AI技術の普及 → 施工管理の効率化が進む
✅ 外国人労働者の増加 → 現場の人手不足を補う鍵に
特に、2025年以降は「経験豊富な職人が大量に引退するため、若手の育成と効率化が急務」となります。
生き残る企業と淘汰される企業の違い
今後、生き残る企業はどんな会社か?
✅ ICTを活用して業務を効率化している
✅ 外国人労働者をうまく活用している
✅ 週休2日制・労働環境の改善を進めている
逆に、「昔ながらのやり方」に固執する会社は淘汰される可能性が高いです。
例えば、「紙ベースで管理」「長時間労働が当たり前」という体制の会社は、若手が定着せず、最終的に人手不足倒産に追い込まれるでしょう。
読者へのメッセージ
あなたは、今後の建設業界でどんな未来を選びますか?
✅ 新しい技術を学び、時代の変化に適応する
✅ 働く環境を見直し、より良い会社を選ぶ
✅ 資格やスキルを身につけて、自分の市場価値を高める
建設業界は確かに厳しい状況ですが、行動を起こせば必ず道は開けます。
10年後に「この業界で生き残ってよかった」と思えるように、今できることから始めてみましょう!
まとめ:人手不足時代の建設業界をどう生き抜くか
✅ 建設業の人手不足は避けられないが、ICTや外国人労働者の活用で対応可能
✅ 企業は働き方改革を進めないと生き残れない
✅ 個人はスキルアップや転職の選択肢を考えるべき
あなたが今すぐできること
1. 会社の状況を確認する
•人手不足が深刻ではないか?
•労働環境は改善されそうか?
2. 自分のキャリアを考える
•資格取得やICTスキルを身につける
•必要なら転職を検討する
3. 情報収集を続ける
•業界の動向をチェックし、早めに行動する
「未来は待っているだけでは変わりません。」
今の自分の選択が、これからのキャリアを左右します。
記事の終わりに
建設業界は確かに厳しい状況ですが、チャンスもたくさんある業界です。
時代の変化に適応し、これからの時代を生き抜くために、あなたの「次の一歩」を踏み出してみてください!
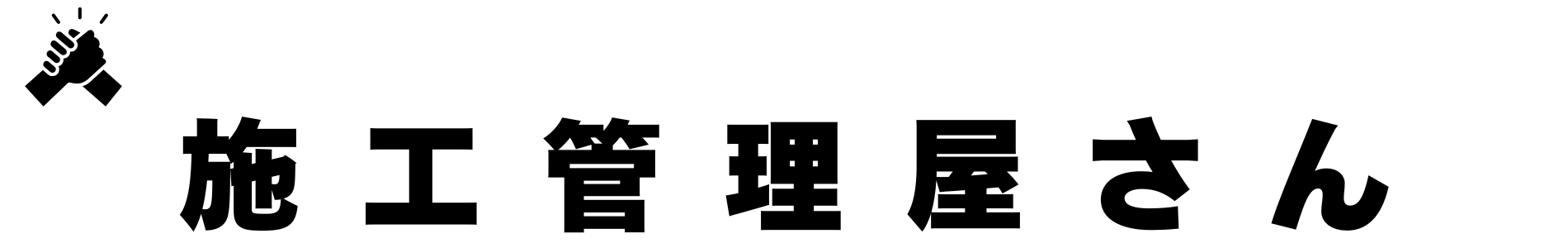
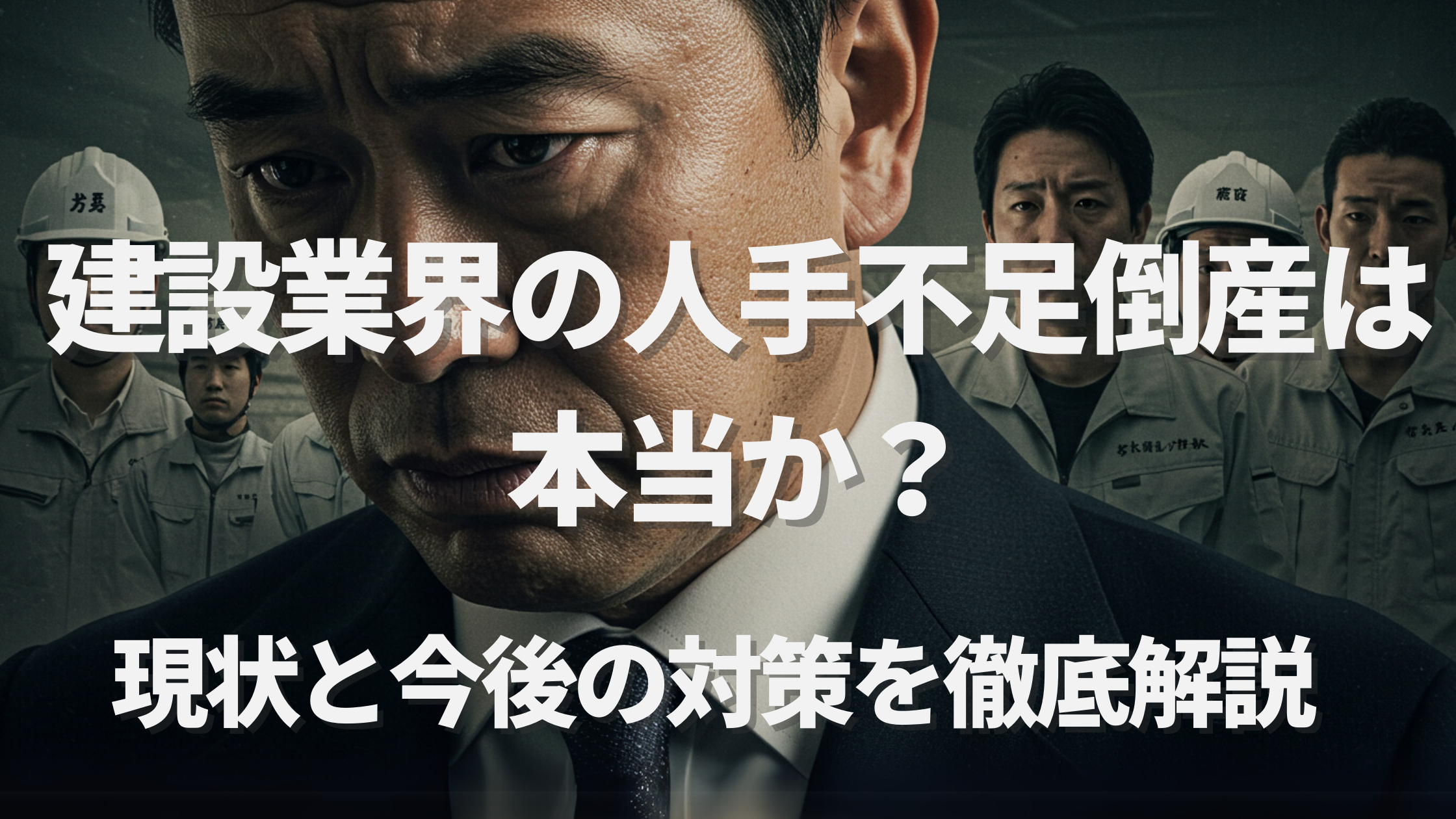

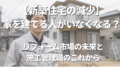
コメント