- とび?設備?現場で飛び交う言葉がわからないあなたへ
- この記事でわかること
- 建設・建築現場の職人とは?
- 具体例:代表的な職人の種類
- 工程順にわかる!職人別の役割と仕事の流れ
- 具体例:工程ごとの職人とその役割
- 新人がつまずきやすい!職人の呼び方と仕事の“ズレ”あるある
- 具体例:よくある“ズレ”のパターン
- 解決策:工程と職種をセットで覚える
- 地域による呼び方の違いもある
- 怖くない!職人さんとの関係の築き方
- 具体例:関係づくりのコツ5選
- よくある誤解:職人さんは怒りっぽい?
- まとめ:敬意とリスペクトがすべて
- 現場監督として知っておくべき「設備工事」の世界
- 具体例:代表的な設備工事の職種と仕事内容
- 設備工事が重要な理由
- 新人が知っておくべきポイント
- 現場監督としての心得
- Q&A
- Q1:うちの現場では一人でいろいろやってる人がいるけど?
- Q2:職人の呼び方って、地域でバラバラじゃない?
- Q3:設備の話って難しそうで苦手…
- Q4:ベテランの職人さん、話しかけにくい…
- Q5:こんなにたくさん職種があるの覚えきれないよ…
- まとめ・行動喚起
- この記事のポイントをおさらい
- まずはできることから:今日の現場で職人さんに声をかけてみよう!
とび?設備?現場で飛び交う言葉がわからないあなたへ
「とび?足場?はつり?設備屋?……正直、現場で何をしている人なのか全然わかりません。」
これは、建設会社に入社して間もない若手現場監督や施工管理技士が、よく口にする言葉です。現場に出ては先輩や職人さんたちの会話を聞いても、知らない単語ばかり。聞きたいけど、聞きにくい。メモは取っているけれど、つながりが見えない――そんな状態ではないでしょうか?
本記事では、建物ができるまでの各工程で登場する職人さんたちの仕事と役割をわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、以下のような悩みを解決できます:
•職人さんの呼び方と、誰がどのタイミングで登場するのかがわかる
•「電気屋さん」や「水道屋さん」が実際にどんな作業をしているのかイメージできる
•地域や現場による違いも考慮しながら、全体の流れをつかめる
この記事でわかること
•現場に登場する主要な職人の種類とその仕事
•建設の流れに沿った工程別の職人さんの登場タイミング
•職人とのコミュニケーションの基本とコツ
•誤解されがちな「設備工事」の世界とその重要性
•よくある疑問・誤解への答えも紹介
「誰がどの仕事をしてくれているのか」を知れば、現場の全体像が見えてきます。
明日からの現場で、きっとあなたの視野が広がるはずです。
建設・建築現場の職人とは?
建設現場では、建物を完成させるために多くの専門職の職人さんが働いています。彼らがいなければ、図面はただの紙のまま。現場は、職人の手で形づくられていくのです。
建物は、一人の職人では完成できません。たとえば鉄筋を組む人、コンクリートを流し込む人、電気を配線する人、壁紙を貼る人……それぞれが専門技術を持ち、工程ごとにバトンを渡すようにして工事が進みます。つまり、建設現場は「専門性の連携プレイ」で成り立っているのです。
具体例:代表的な職人の種類
| 職種 | 主な作業内容 |
| 土工(どこう) | 重機で掘削・埋戻し・整地などを行う基礎の準備役 |
| 鉄筋工 | 建物の骨格となる鉄筋を正確に組む |
| 型枠大工 | コンクリートを流すための枠(型枠)を作成・設置 |
| とび職(鳶) | 足場の組立や高所作業の準備、安全確保を担当 |
| 大工 | 木造の骨組みや下地作り、サッシ・建具の設置などを担当 |
| 左官 | 壁や床の下地を塗る・平らに仕上げる |
| 塗装職人 | 建物の外壁や内装に塗装を施して美観と保護を両立 |
| 電気工事士 | 電気配線、コンセント、照明の設置など |
| 設備工事職人 | 水道・空調・ガスなど、生活に必要なインフラを整備する |
これだけの職人さんたちが、それぞれの「タイミング」で現場に入ってきます。
彼らの役割と順番を知らないままでは、現場をスムーズに回すことができません。
次章では、建物が完成するまでに登場する職人の「順番」を、工程ごとに詳しく解説します。
工程順にわかる!職人別の役割と仕事の流れ
建物が完成するまでには、明確な工程の順番があります。
それに合わせて、職人さんたちも次々と現場に登場します。
工程を理解し、どの職人がどのタイミングで何をするのかを把握しておくと、段取りがよくなり、現場全体の管理もしやすくなります。
現場監督として「誰に、いつ、何を頼めばいいのか」が見えてくるようになります。
具体例:工程ごとの職人とその役割
① 地盤工事・基礎工事に関わる職人
| 職種 | 役割・作業内容 |
| 土工(どこう) | 整地、掘削、砕石敷きなどの「地面の準備」 |
| 鉄筋工 | 建物の強度を決める鉄筋の配筋 |
| 型枠大工 | コンクリートを流し込む「型」を木材などで組み立てる |
| コンクリート工 | 型枠にコンクリートを流し込み、振動機で空気を抜く |
② 躯体工事・骨組みを作る職人
| 職種 | 役割・作業内容 |
| 鳶職(とび) | 足場の組立、高所作業の補助、安全設備の設置 |
| 大工・鉄骨工 | 木造なら大工、鉄骨造なら鉄骨工が柱や梁を組む |
| クレーンオペレーター | 重量物の吊り上げ・資材の運搬 |
③ 外装・内装工事の職人
| 職種 | 役割・作業内容 |
| 屋根屋 | 防水シートや瓦などを使って屋根を仕上げる |
| 外壁工 | 外壁材(サイディング、ALCなど)を取り付け |
| 左官職人 | 壁や床の表面をモルタルや漆喰でなめらかに整える |
| クロス職人 | 壁紙を貼って仕上げを行う |
| 建具工 | ドアやサッシの設置、調整を担当 |
④ 設備工事の職人
| 職種 | 役割・作業内容 |
| 電気工事士 | コンセント・照明・分電盤の設置 |
| 管工事職人(水道・ガス) | 給排水管の設置、ガス配管の接続 |
| 空調設備工 | エアコン・換気扇の設置、ダクト工事 |
| 機械器具設置工 | エレベーターや自動ドアなどの据え付け |
⑤ 最終仕上げ・検査に関わる業者
| 職種 | 役割・作業内容 |
| 検査機関スタッフ | 消防検査、避難経路のチェックなど |
| 測量士 | 敷地境界や高さの確認、竣工図との照合 |
| 引き渡し業者 | 操作説明、保証書の交付など |
このように、建設の現場は職人さんのバトンリレーで成り立っています。
工程ごとに「誰が何をするのか」を把握しておけば、無駄な待機やミスを減らすことができ、現場全体の品質もアップします。
新人がつまずきやすい!職人の呼び方と仕事の“ズレ”あるある
現場でよく聞く職人の呼び方が、仕事の内容と一致していないように感じることはありませんか?
それ、あなただけではありません。実は、職人の「呼び方」や「担当範囲」は、地域や現場によってかなりズレがあるのです。
建設業界では、現場ごとに文化や呼び方が違うことが多くあります。
たとえば、同じ「とび職」でも、ある現場では「足場専門」、別の現場では「鉄骨もやる」など、職人さんの守備範囲が違います。
これは、地域の慣習や、職人さん自身のスキル、元請けの考え方などに影響されているからです。
具体例:よくある“ズレ”のパターン
| 呼び方 | 新人が思う仕事 | 実際の現場でのパターン |
| とび職 | 足場を組む人 | 足場だけでなく、鉄骨建方やクレーン誘導まで担当することも |
| 設備屋さん | 水道屋?電気屋?空調? | 電気・水道・ガス・空調など、設備系全体をひとくくりにされることが多い |
| 大工さん | 木を使う人? | 木造住宅では全体を担うが、RC造ではちょっとしか出番がないことも |
| はつり屋さん | 何をしてるの? | コンクリートを壊したり、凹凸を削って表面を整える専門職 |
| 内装屋さん | 壁紙を貼る人? | クロス貼り、間仕切り、床材、天井などを一括で指すことがある |
解決策:工程と職種をセットで覚える
職人さんの仕事を理解するコツは、「呼び名」よりも工程とセットで覚えることです。
たとえば…
•基礎工事=鉄筋工+型枠大工+コンクリート工
•内装工事=左官+クロス+建具工
というように、「どの段階で・どの職人が・何をするか」を流れで捉えると、頭の中が整理されます。
地域による呼び方の違いもある
たとえば「とび職」は、関東では足場専門のイメージが強いですが、関西では鉄骨建方も含めて総合的に扱うことが多いです。
また、「防水屋さん」を「塗膜屋さん」と呼ぶ現場もあります。
こうした違いに戸惑うかもしれませんが、共通の言語を持つためには、「仕事の中身」に注目することが一番の近道です。
怖くない!職人さんとの関係の築き方
「職人さんって怖そう…」「怒られそうで話しかけづらい…」
そんな不安、よくわかります。ですが、職人さんとの関係は、ちょっとした工夫でグッと良くなります。
現場の仕事はチーム戦です。職人さんとの信頼関係があるかどうかで、作業の進み具合や報告のしやすさが大きく変わります。
丁寧に接してくれる監督には、職人さんも自然と協力的になります。逆に、指示があいまいだったり、現場を見ていない監督には、なかなか本音を話してくれません。
具体例:関係づくりのコツ5選
| ポイント | 解説 |
| 1. 挨拶は自分から | 「おはようございます」「お疲れ様です」を元気よく。基本だけど一番大事。 |
| 2. 名前を覚える・呼ぶ | 「○○さん、明日この配管の確認お願いできますか?」と名前で呼ぶだけで関係が変わります。 |
| 3. 作業中は“手が空いたときに”話す | 手を止めさせるのはNG。声をかけるタイミングを見極めることも信頼につながります。 |
| 4. わからないことは正直に聞く | 「すみません、それどういう意味ですか?」と素直に聞けば、教えてくれる職人さんは多いです。 |
| 5. 小さな感謝を伝える | 「助かりました!」「早かったですね!」など、気づいたらすぐ伝えましょう。小さな一言が関係をつくります。 |
よくある誤解:職人さんは怒りっぽい?
確かに、現場で怒っているように見える人もいます。でもそれは、工期のプレッシャーや安全への責任感からくる真剣さです。
話してみれば、意外とフランクで優しい人が多いのが現実です。
まとめ:敬意とリスペクトがすべて
職人さんは「現場のプロフェッショナル」です。
だからこそ、敬意を持って接することが、信頼関係の第一歩になります。
「現場をうまく回す力」は、技術だけでなく人とのつながりでも養われます。
まずは、今日の現場で「おはようございます!」から始めてみましょう。
現場監督として知っておくべき「設備工事」の世界
建物を「使える状態」に仕上げるために、設備工事は絶対に欠かせない工程です。
電気・水道・空調・通信など、目に見えにくい部分を整えるこの工事は、現場監督として絶対に理解しておきたい領域です。
建物が「建った」だけでは、住んだり使ったりはできません。
スイッチを押せば電気がつき、水が出て、エアコンが動く――そんな当たり前の機能は、設備工事のおかげです。
また、設備工事は建物の後半工程で集中して進むため、他職種との取り合い(干渉)も多く、段取り次第で全体の進行に大きく影響します。
具体例:代表的な設備工事の職種と仕事内容
| 職種 | 主な作業内容 | よく聞く呼び名 |
| 電気工事士 | 照明、コンセント、分電盤の設置。幹線ケーブルの配線。 | 電気屋さん |
| 管工事職人 | 給水・排水・ガス配管の接続、機器の取り付け。 | 水道屋、ガス屋 |
| 空調設備工 | エアコンの設置、ダクトの取り付け、冷媒管の配管など。 | 空調屋さん |
| 通信工事業者 | LAN配線、電話線、防犯カメラ、インターホンなど。 | 弱電屋さん |
| 機械器具設置業者 | エレベーター、ポンプ、換気機器などの設置。 | 機器屋さん |
設備工事が重要な理由
•生活インフラの心臓部
→ 設備がなければ、建物は機能しません。
•複数業種が入り乱れる
→ 天井裏や床下など、狭い空間での作業が多く、工程の調整力が求められる。
•設備図面は施工図が命
→ 他の工事と干渉しないよう、事前の図面チェックや打ち合わせが超重要。
新人が知っておくべきポイント
•「どの職人が、どの機器を取り付けるのか」を明確にする
→ 例:換気扇は空調屋?機器屋?
•機器設置前の下準備が多い
→ 配管や配線は、仕上げ工事の前に終えておかないとやり直しに…
•“先行配管・先行配線”の意味を理解しておく
→ コンクリート打設前、壁を貼る前など、タイミングが非常に重要!
現場監督としての心得
設備工事は、「目に見えにくいけど、失敗が目立つ」工種です。
図面通りに進めるのはもちろんのこと、「先を読む段取り力」こそが、現場監督としての評価を決めるポイントになります。
Q&A
この記事を読んでいるあなたの中には、
「うちの現場ではちょっと違うんだけど…?」と感じた方もいるかもしれません。
ここでは、よくある疑問や反論に先回りしてお答えします。
Q1:うちの現場では一人でいろいろやってる人がいるけど?
A:それ、たぶん「多能工(たのうこう)」さんです。
多能工とは、複数の職種をまたいで仕事ができる職人さんのこと。
特に小規模現場や改修工事ではよく見られます。
ただし、建物の新築や中規模以上の工事では、工程の効率化や専門性の高さが求められるため、基本的には分業が前提になります。
一人で何でもできるのはすごいことですが、全てを任せるには限界もあります。
Q2:職人の呼び方って、地域でバラバラじゃない?
A:はい、地域差や業者ごとの言い回しはけっこうあります。
たとえば、
•「とび職」を「足場屋」と呼ぶ現場
•「防水屋さん」と「塗膜屋さん」が同じだったり別だったり
•「弱電屋さん」と「通信業者」が混同されていたり
でもご安心ください。
基本的な職種や作業内容は全国で大きくは変わりません。
名前に惑わされず、「その人が何をしているか」を観察するクセをつけると理解が早くなります。
Q3:設備の話って難しそうで苦手…
A:それ、最初はみんなそうです。でも「流れ」で覚えると案外簡単。
たとえば、
•コンクリート打つ前に「先行配管」
•壁を貼る前に「配線」
•電気通す前に「分電盤のチェック」
など、「この作業の前にこれが必要」という“段取りの順番”で理解すると、スッと頭に入ってきます。
難しいことを覚えるより、工程の流れと「どの職人さんがそこに関わるか」を意識することがポイントです。
Q4:ベテランの職人さん、話しかけにくい…
A:確かに最初は緊張します。でも「一言の挨拶」が一番の武器です。
「お疲れ様です、○○の件なんですけど…」と声をかけるだけで、ほとんどの職人さんは話を聞いてくれます。
それでも不安なときは、現場に長くいる中堅職人さんや職長さんに先に相談してから話を通すのも有効です。
Q5:こんなにたくさん職種があるの覚えきれないよ…
A:最初から全部覚える必要はありません。
まずは「今、現場にいる人が何をしているか」を観察するところから始めましょう。
写真や日報を見返しながら、「この人たちはこの工程に関わってたんだな」と少しずつ理解を積み上げることが大切です。
どんな疑問も、ひとつずつ解決していけばOKです。
焦らず、でも確実に、「わかる現場監督」になっていきましょう。
まとめ・行動喚起
この記事では、建設・建築業界で働く新人現場監督や施工管理技士のために、職人別に仕事内容や役割、登場する工程の順番などを詳しく解説してきました。
この記事のポイントをおさらい
•現場では専門職の職人がバトンをつなぐように作業している
•呼び名や仕事の範囲は地域や現場でズレがあるが、「工程ごとの役割」で理解すれば整理しやすい
•職人さんとの信頼関係づくりは、挨拶・名前・感謝の言葉から始まる
•設備工事は建物を「使える」状態にする要の工程。図面と段取りが命
•わからないことは、現場で一つずつ見て、聞いて、覚えていけばOK
この記事を通じて、あなたは「誰が、いつ、何をしているのか」が見えるようになったはずです。
それは、現場を“指示できる”力の第一歩。
これからの現場で、職人さんと対等に会話し、工程をコントロールしていく力になります。
現場監督として「何屋さんなのかすらわからない…」というモヤモヤは、最初は誰にでもあるものです。
でも、あなたが知ろうとする姿勢を見て、職人さんたちは必ず応えてくれます。
明日からの現場で、ぜひ「この人は何をしているんだろう?」と観察してみてください。
わかると、現場はどんどん楽しくなってきます。
まずはできることから:今日の現場で職人さんに声をかけてみよう!
•「おはようございます」から始める
•休憩時間に話しかけてみる
•目の前の工事が何かを調べてみる
小さな行動が、あなたを“できる現場監督”へと導いてくれます。
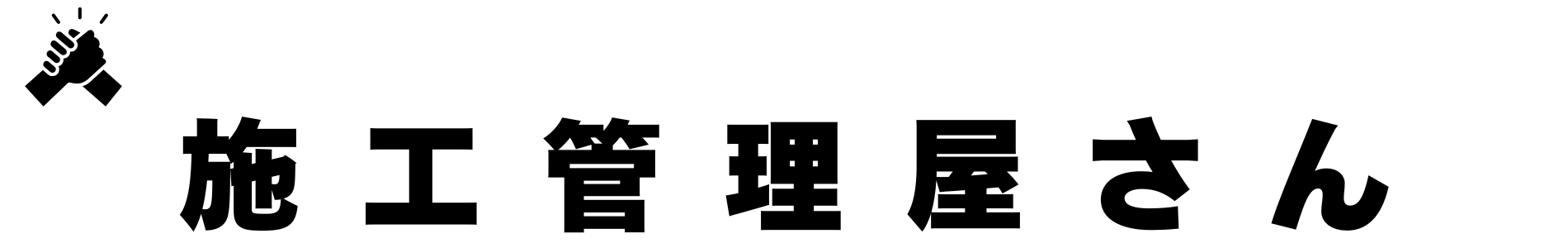



コメント