- 1. はじめに
- 2. 新築住宅の減少は本当?最新データをもとに解説
- 2-1. 住宅着工統計の最新動向(2024〜2025年)
- 2-2. なぜ新築住宅が減少しているのか?
- 2-3. 今後、新築住宅はどうなるのか?
- まとめ
- 3. 施工管理職の未来はどうなる?新築が減っても仕事はあるのか
- 3-1. リフォーム市場の拡大と施工管理の新たな役割
- 3-2. 相続による新築需要はどうなる?
- 3-3. 施工管理としての新しいキャリアの可能性
- まとめ
- 4-1. 「新築が減る=仕事がなくなる」ではない
- 4-2. これからの施工管理職に求められるスキルとは?
- 4-3. これからの施工管理職が考えるべきキャリアの選択肢
- 4-4. まとめ:施工管理職は未来にどう備えるべきか?
- 5. 行動を促すメッセージ
1. はじめに
最近、「新築の着工件数が減っている」と感じる施工管理職の方は多いのではないでしょうか?
実際、少子化や経済状況の変化により、新築住宅の建設は年々減少しています。統計データを見ても、新築住宅の着工戸数は15年以上減少傾向が続いており、「家を建てる人がいなくなる時代が来るのでは?」という不安の声も聞かれます。
では、新築が減ると住宅業界の仕事はなくなるのでしょうか? 施工管理の仕事も厳しくなるのでしょうか?
結論から言うと、住宅業界の変化は確かに起こっていますが、それが必ずしも「仕事がなくなる」ことを意味するわけではありません。むしろ、新築からリフォームやリノベーションへと市場がシフトしている今こそ、新しいチャンスが生まれているのです。
本記事では、最新の住宅着工統計をもとに新築住宅の減少の現状と背景を解説し、施工管理職の未来について考えていきます。
2. 新築住宅の減少は本当?最新データをもとに解説
「最近、新築住宅が減っている」と感じる施工管理の方も多いでしょう。実際に、新築着工数はどの程度減少しているのでしょうか?ここでは、最新の統計データをもとに、新築住宅の現状とその背景を解説します。
2-1. 住宅着工統計の最新動向(2024〜2025年)
国土交通省の「建築着工統計調査」によると、2025年1月の新設住宅着工戸数は前年同月比4.6%減の5万6,134戸でした。これで9か月連続の減少となり、新築住宅市場の縮小が続いていることがわかります。
住宅種別ごとの変化
| 住宅種別 | 2025年1月の着工戸数 | 前年同月比 |
| 持家(個人所有住宅) | 13,525戸 | 8.6%減 |
| 貸家(賃貸住宅) | 24,710戸 | 1.2%減 |
| 分譲住宅 | 17,899戸 | 6.0%減 |
持家の減少幅が大きく、特に「個人が家を建てる」ケースが減っていることがわかります。
また、2024年の年間着工戸数は**79万2,070戸(前年比3.4%減)**となり、リーマンショック後の2009年以来15年ぶりに80万戸を下回る結果となりました。
地域別の動向
| 地域 | 着工戸数の増減率 |
| 北海道 | 16.8%増(回復傾向) |
| 四国 | 28.7%減(大幅減少) |
北海道ではやや回復傾向が見られるものの、四国地方では約3割の落ち込みが発生しており、地域によって状況は大きく異なっています。
2-2. なぜ新築住宅が減少しているのか?
新築住宅の着工が減少している背景には、以下のような要因が考えられます。
① 少子化と人口減少
日本の人口はすでに減少局面に入り、2030年以降は世帯数そのものが減少すると予測されています。
ポイント
・世帯数が減れば、新たに家を建てる需要も減る
・特に地方では空き家が増え、新築の必要性が低下
② 建築コストの高騰
近年の建築資材価格の上昇も、新築が減る大きな要因です。
データ:2024年の建材価格
・前年比15%上昇(特に木材・鉄筋が高騰)
・工務店の利益圧迫 → 新築の建築コストが増加
「家を建てたい」と思っても、建築コストの増加により資金計画が難しくなり、新築を断念するケースも増えています。
③ 中古住宅市場の拡大
これまでは「家を建てる=新築」という考えが主流でしたが、最近では中古住宅の流通が増え、リフォーム・リノベーションの需要が高まっています。
背景
・政府の「中古住宅流通促進策」により、中古住宅市場が拡大
・リフォーム補助金制度などを活用することで、新築より低コストで住宅を取得できる
特に都市部では、「新築を買うより中古住宅をリノベーションしたほうがコスパがいい」と考える人が増えており、新築の需要が減少しています。
2-3. 今後、新築住宅はどうなるのか?
では、今後も新築住宅の減少は続くのでしょうか?
専門機関の予測
| 年度 | 予測着工戸数(万戸) | 予測機関 |
| 2025年度 | 78.4万戸 | 三菱UFJリサーチ |
| 2030年度 | 74万戸 | 野村総合研究所 |
| 2040年度 | 58万戸 | NRI(ベースシナリオ) |
上記の予測を見ると、2025年以降も新築住宅は減少し、2040年には現在より20万戸以上減る可能性があることがわかります。
つまり、新築住宅の減少は一時的なものではなく、長期的なトレンドとして続いていくと考えられます。
まとめ
•新築住宅の着工数は9か月連続減少し、2024年は15年ぶりに80万戸を下回った
•少子化・建築コストの上昇・中古住宅市場の拡大が主な原因
•2040年には新築住宅の着工数が約58万戸まで減少すると予測されている
新築住宅が減っていく中で、施工管理の仕事はどう変わるのか?
次の章では、「施工管理職の未来」について解説していきます。
3. 施工管理職の未来はどうなる?新築が減っても仕事はあるのか
新築住宅の着工数が減少していることは事実ですが、それによって施工管理の仕事がなくなるわけではありません。むしろ、住宅市場の変化に適応することで、新しいキャリアのチャンスが広がっています。ここでは、施工管理職の未来について解説します。
3-1. リフォーム市場の拡大と施工管理の新たな役割
新築が減少する一方で、リフォーム市場は拡大しています。
リフォーム市場の成長
•2024年のリフォーム市場規模は約8兆円(前年比5%増)
•既存住宅のリノベーション需要が高まり、2025年には10兆円規模に拡大すると予測
•中古住宅の流通増加に伴い、施工管理の仕事も「新築」から「リフォーム」へシフト
これまでの施工管理の仕事は**「ゼロから建てる」ことが中心でしたが、今後は「既存の建物を活かしながら価値を向上させる」**方向に変化していきます。
施工管理の新たな役割
•リノベーション工事の管理(耐震補強・間取り変更・水回り改修など)
•省エネ・スマート住宅化の推進(ZEH・IoT設備の導入)
•住宅の長寿命化対応(外壁・屋根・断熱材の改修)
リフォームは「決まった設計図通りに建てる」新築とは違い、現場ごとに異なる状況を考慮した柔軟な施工管理スキルが求められます。
3-2. 相続による新築需要はどうなる?
「相続で住宅需要が増えるのでは?」という声もありますが、新築市場への影響は限定的です。
相続税対策としての賃貸住宅建設
•相続税評価を抑えるための賃貸住宅建設が一定数存在
•2024年の賃貸住宅着工数は34万2,025戸(横ばい傾向)
•ただし、相続物件の30%以上が空き家化しており、新築ではなくリフォームへシフト
2024年1月からの税制改正により、相続税対策としての賃貸住宅建設のメリットが縮小。これにより、2025年以降の**「相続×新築」需要は10〜15%減少する**と予測されています。
今後、施工管理の仕事は「相続による新築」よりも、「相続物件のリフォーム・リノベーション」にシフトしていく可能性が高いです。
3-3. 施工管理としての新しいキャリアの可能性
新築が減少する一方で、施工管理としての新しい働き方が求められています。
① 省エネ住宅・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)への対応
•2030年以降、新築住宅のZEH基準適用が義務化
•高断熱・高気密住宅の施工技術が求められる
•補助金・助成制度を活用した省エネ改修が増加
→ 施工管理として、省エネ技術や補助金制度の知識を身につけると強みになる
② 木造・プレハブ・スマート住宅の技術習得
•木造住宅の比率が68%(2024年)と過去10年で最高値
•プレハブ住宅の市場規模は前年比5.3%増と堅調
•スマートホーム技術(IoT・AI)の導入が進み、施工管理の業務範囲が拡大
→ 最新技術を取り入れた住宅の施工管理に関わることで、仕事の幅が広がる
③ リフォーム・リノベーションの専門知識を深める
•水回り・外装・耐震補強・バリアフリー改修のニーズが増加
•住宅ストックの長寿命化に向けた「維持・管理」スキルが重要に
•中小工務店でも「リフォーム専門施工管理者」の需要が高まっている
→ 施工管理として「リフォーム・リノベーションのプロ」を目指す選択肢もある
まとめ
•新築が減っても、リフォーム市場の拡大により施工管理の仕事はある
•相続による新築需要は限定的で、リフォーム・リノベーションが主流になる
•省エネ住宅・スマート住宅・リフォームの施工管理が今後のキャリアのカギ
施工管理の仕事は「新築だけ」ではなく、住宅市場の変化に対応することで新しいチャンスが生まれるのです。
4. まとめ:施工管理職はどうキャリアを考えるべきか?
新築住宅の着工数は減少傾向にありますが、それによって施工管理の仕事がなくなるわけではありません。むしろ、住宅業界の変化に適応することで、新しいキャリアの選択肢が広がる時代です。
では、今後の施工管理職はどのようにキャリアを考えるべきなのでしょうか?
4-1. 「新築が減る=仕事がなくなる」ではない
新築住宅が減少しているのは事実ですが、住宅業界全体が縮小しているわけではありません。
以下のように、新しい施工管理の需要が生まれています。
✅ リフォーム・リノベーション市場の拡大
•住宅の「量」から「質」へシフト
•既存住宅の改修・耐震補強・省エネ改修の需要が増加
•2025年にはリフォーム市場は10兆円規模に拡大
✅ 省エネ住宅・ZEH・スマート住宅の施工管理
•2030年以降、新築住宅のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)義務化
•省エネ基準を満たした住宅の施工管理スキルが求められる
•IoT・AIを活用したスマート住宅の施工も増加
✅ 施工管理の専門性がより重要に
•「新築からリフォームへ」の流れで施工管理の役割が多様化
•住宅の長寿命化を見据えた技術や知識が求められる
→ 施工管理の仕事は「新築だけ」ではなく、住宅市場の変化に応じてシフトしていくことで、今後も十分に需要がある!
4-2. これからの施工管理職に求められるスキルとは?
施工管理としてのキャリアを考える上で、これからの時代に役立つスキルを身につけることが重要です。
① リフォーム・リノベーションの知識を深める
•耐震補強・バリアフリー改修・水回り改修の技術習得
•補助金・助成制度の活用を理解し、顧客に提案できるスキル
② 省エネ住宅・スマート住宅の施工技術を学ぶ
•ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準の理解
•IoT・AIを活用した住宅設備の施工管理
③ 施工管理のIT化・DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応
•施工管理アプリの活用(写真管理・工程管理・発注管理)
•ドローン・3Dスキャンなど、新技術の活用
✅ 「従来の施工管理」+「新しい技術や知識」を学ぶことで、今後のキャリアの幅が広がる!
4-3. これからの施工管理職が考えるべきキャリアの選択肢
新築が減少する中で、施工管理職が目指せるキャリアの方向性は大きく3つあります。
① リフォーム・リノベーション専門の施工管理
•既存住宅の改修・耐震補強・断熱改修などの専門知識を活かす
•戸建て・マンションのリノベーション専門の施工管理を目指す
おすすめの資格:
🏡 既存住宅状況調査技術者
🏡 建築施工管理技士
② 省エネ・スマート住宅の施工管理
•ZEH住宅・IoT住宅・スマートハウスの施工管理に関わる
•今後の市場ニーズが拡大する分野でキャリアアップ
おすすめの資格:
🌱 ZEH(ゼロエネルギーハウス)マスター講習
🌱 BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価員
③ 施工管理のDX(デジタル化)に対応
•施工管理アプリ・ドローン・AI活用などの最新技術を学ぶ
•ITを活用できる施工管理者として市場価値を高める
おすすめのスキル習得:
💻 施工管理アプリ(ANDPAD・ダンドリワーク)を使いこなす
💻 ドローン測量・3Dスキャン技術を習得
✅ 「施工管理×新しい技術」を学ぶことで、業界の変化に対応できる人材になれる!
4-4. まとめ:施工管理職は未来にどう備えるべきか?
✅ 新築住宅の減少=施工管理の仕事がなくなるわけではない
✅ リフォーム・リノベーション、省エネ住宅、DXなど新しい分野での需要が拡大
✅ これからの施工管理職は「変化に対応できるスキル」を身につけることが重要
これからの住宅業界は、「新築からリフォームへ」「量から質へ」「アナログからデジタルへ」と変化しています。
施工管理職としてキャリアを築くためには、今後の市場の動向を理解し、新しい技術・知識を学び続けることがカギになります。
5. 行動を促すメッセージ
「焦る必要はありません。施工管理のスキルは一生ものです。」
変化に対応できる施工管理者こそが、これからの時代に求められる人材です。
✅ リフォーム・リノベーションの知識を深める
✅ 省エネ住宅・スマート住宅の技術を学ぶ
✅ IT・DXを活用し、施工管理の仕事を効率化する
「これからの住宅業界の変化を知り、あなたのキャリアを考えるきっかけにしてほしい。」
まずは、自分ができることから一歩を踏み出しましょう!
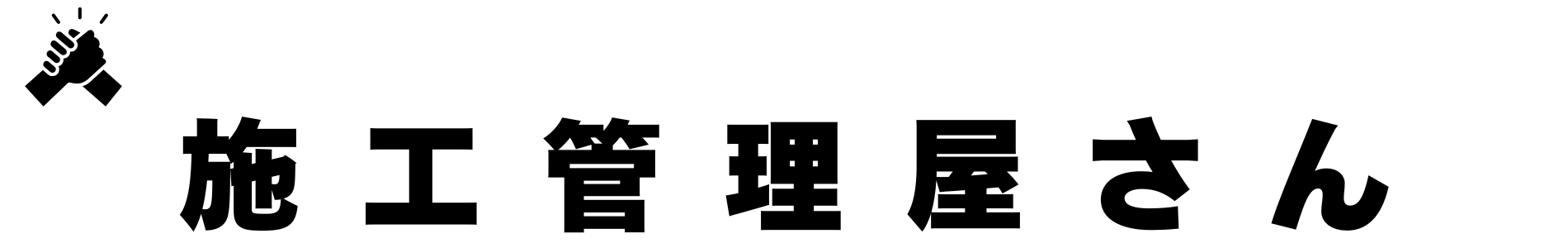
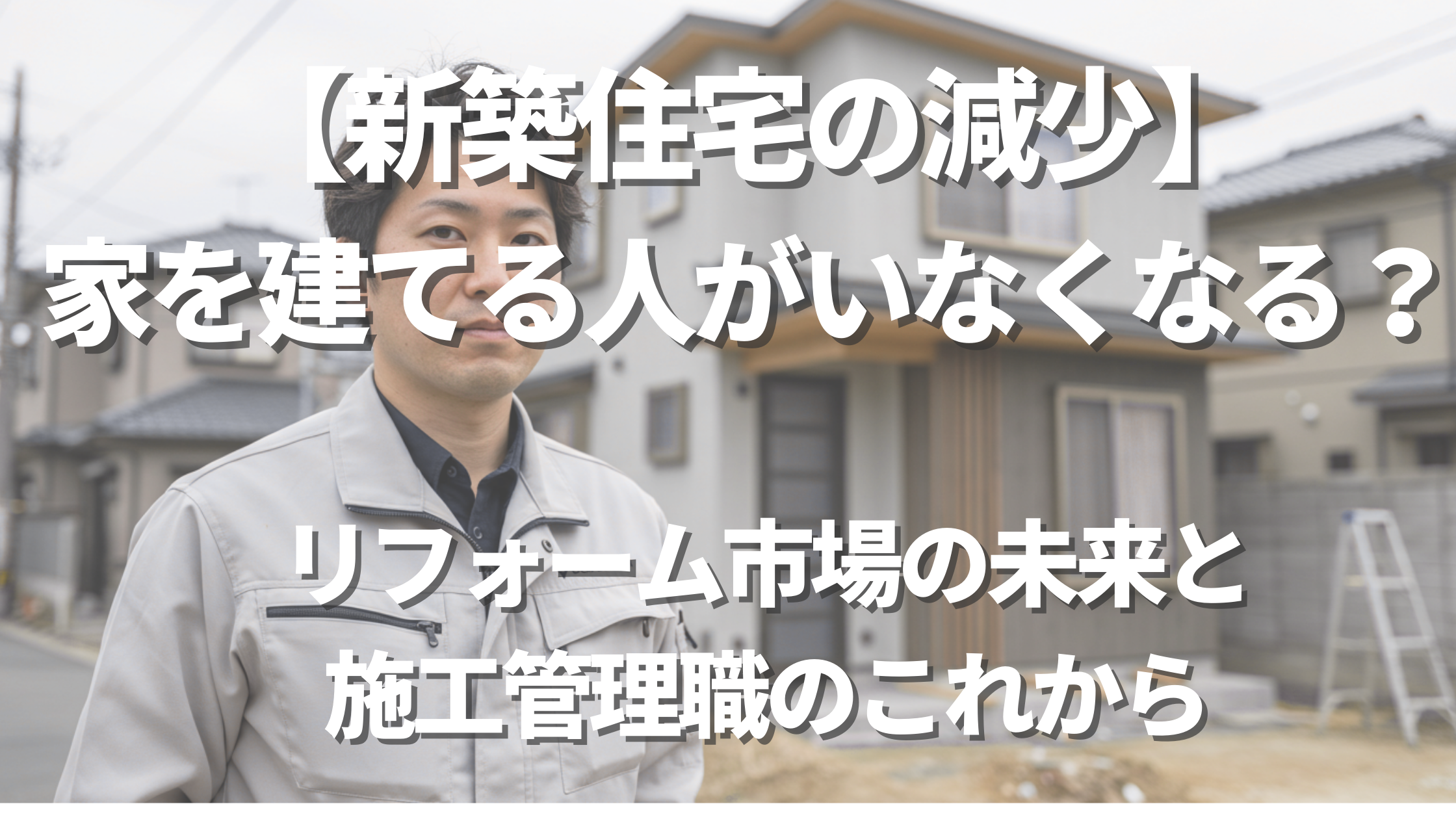
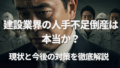

コメント